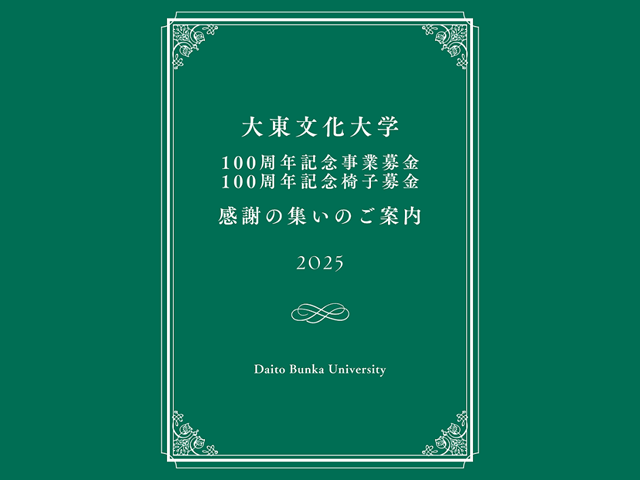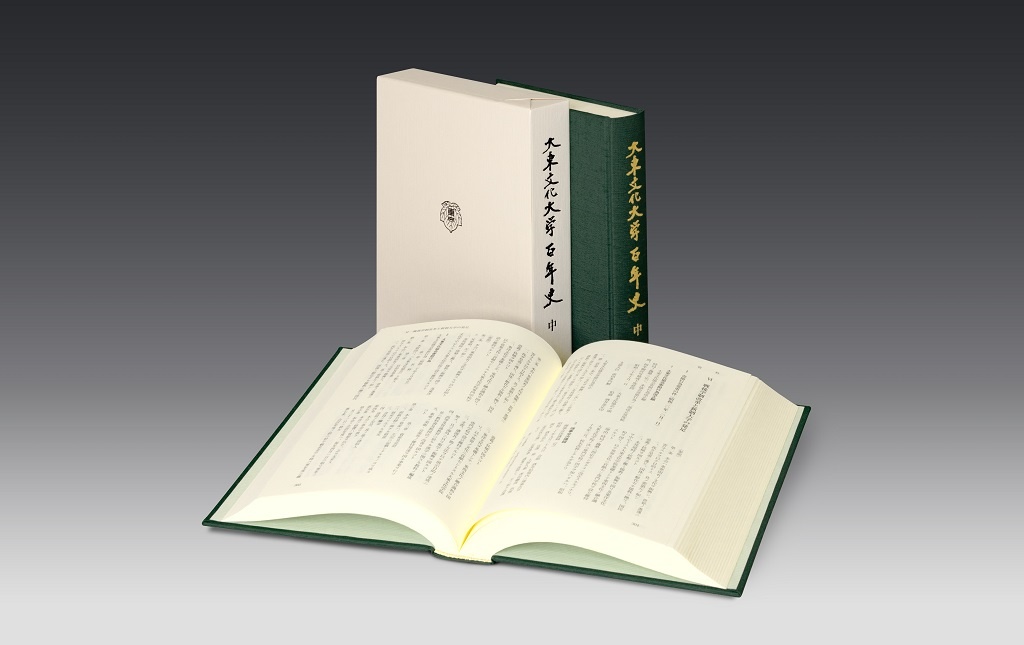2020.10.14
まんなか学部 100周年特別企画 第2弾 古典文化や伝統芸能を習得する難しさと追求していく面白さ
■プロフィール
●佐藤 陽香(さとう はるか) 将棋研究会
文学部 日本文学科3年 福島成蹊高等学校 出身
●橋本 冴音 (はしもと さおと) 琴和道会 幹事長
国際関係学部 国際文化学科3年 東京農業大学第三高等学校 出身
●大川 楓佳(おおかわ ふうか) 落語研究会
文学部 日本文学科2年 群馬県立桐生女子高等学校 出身
ルールの複雑な将棋と伝統的な和楽器
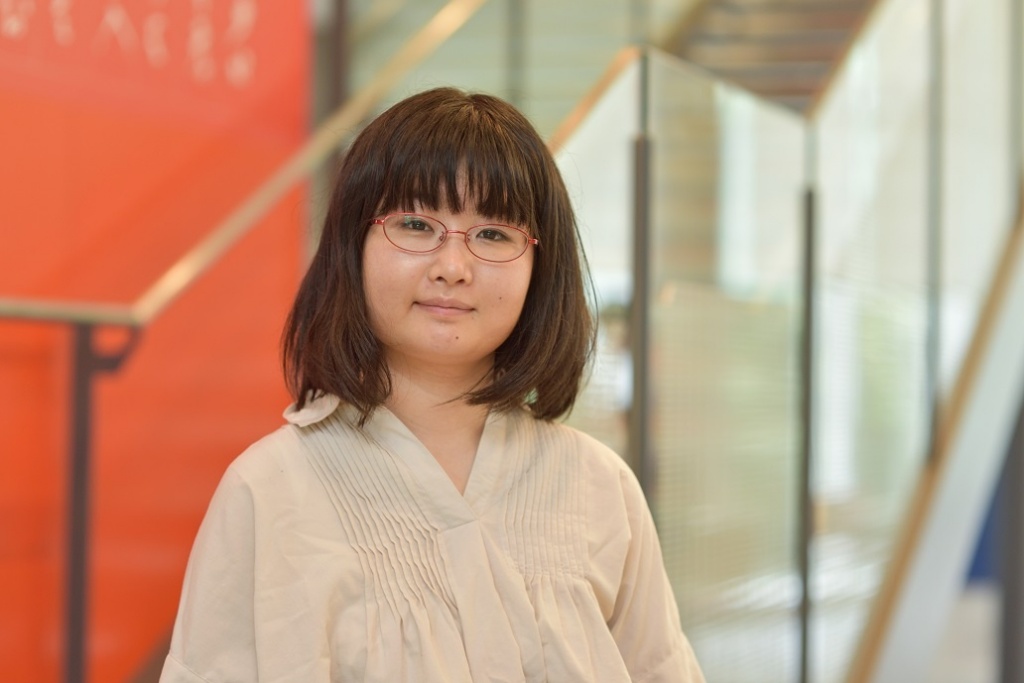 佐藤陽香さん(将棋研究会)
佐藤陽香さん(将棋研究会)
──佐藤さんが将棋を始めたきっかけについてお聞かせください。
佐藤陽香さん(以下、佐藤):小学生の時に父に習ったのがはじまりです。大会に出場したら勝てたので、本格的に取り組むようになりました。ただ高校まで将棋部がない学校に通っていたので、こうして部活に入ったのは大学からです。
──将棋研究会には佐藤さんのほかにも女子学生はいますか?
佐藤:ほとんどが男子で、女子の部員は3~4人です。ルールが難しいので、その最初の段階で興味を持つ人とそうでない人に振り分けられちゃうかもしれません。
*佐藤さんは福島成蹊高校2年次に全国高校将棋新人大会で5位入賞、東北地区高校将棋新人大会でも2連覇の記録があります。
──橋本さんや大川さんは、将棋を指したことはありますか?
橋本冴音さん(以下、橋本):私はさっぱりわかりません。
大川楓佳さん(以下、大川):小学生の時に学童保育でシルバー人材センターの方に教わりました。駒の進み方は覚えましたが、駒が裏返るとわからなくなってしまいます(笑)。もっとも、駒が裏返る前に負けてしまいますけど。
佐藤:成る(相手の陣地に自陣の駒が入り裏返ること)ことができない駒もあるので、そこもややこしいところです。
──琴和道会で幹事長を務める橋本さんにお聞きします。「冴音」というお名前からして、まさに音楽を奏でるために生まれてきたのでは、と言われるかと思いますが。
橋本:よく言われますが、名前負けしていると思います(笑)。入学を機に、新しいことにチャレンジしたいと考えていたところ、本学で唯一和楽器を扱っている琴和道会を知り興味を持ちました。未経験のジャンルでしたが、説明会などを通して、部員同士の温かい雰囲気にも惹かれて入部を決めました。
──技術的な不安はありませんでしたか?
橋本:私はお筝と、十七弦というふつうのお筝より弦の本数が多いものを担当しています。技術的な面では、新型コロナウイルスの影響を受ける前は、月に4回、外部講師を招いてのお稽古があり、基本的な技術から上達の度合いに応じてご指導をいただいていたので、初心者でもまったく問題ありませんでした。しかし、現在は部員それぞれ自宅で出来る範囲の自己練習のみとなっています。今後については、社会情勢や感染症対策等をよく考慮し、外部講師による指導の再開を考えています。
──「琴」と「筝」の違いに教えていただけますか?
橋本:「音程を調整するための『柱(じ)』があるのが『筝』で、ないものが『琴』です。琴和道会では主に、筝と三味線と尺八による三曲という音楽を扱っています。三曲とは、江戸時代から続く日本の代表的な伝統音楽ですが、専門家による芸術音楽としての側面のほか、私たちでも気軽にできる家庭音楽として広く普及しています。
*三曲:日本において、江戸時代から最も普及している3種類の音楽=「箏(そう)曲」といわれる箏(こと)の音楽、「地歌(じうた)」といわれる三味線(しゃみせん)の音楽、「尺八(しゃくはち)」の音楽の総称。
視聴者から作り手の立場になってはじめて見えてくるもの
 橋本冴音さん(琴和道会)
橋本冴音さん(琴和道会)
──落語研究会の大川さんにお聞きします。いわゆる「落研」ですが、近頃は落語よりもお笑いのほうに寄っているというのはいまどきの傾向でしょうか?
大川:漫才やコント、あとピンネタをする人が多いですね。落語研究会の歴史について先輩方にたずねたところ、確かなことはわかりませんでしたが、昔は落語のほうが盛んだったようです。もちろん現在でも落語に専念している部員はいます。
──落語だと古典を覚えたりして時間がかかりますから、コントなんかのほうが入りやすいのでしょうか?
大川:それぞれ違った難しさはあると思います。落語は数百年にわたり受け継がれている文化ですから、その伝統を踏まえたうえで自分の色を出していかなければなりません。漫才やコントは自分たちで一から創り上げる難しさがあります。両者ともに、それを追求することに面白さとやりがいを感じます。
──一番のお披露目の舞台は大東祭ですか?
大川:はい、3日間で5公演行いますが、けっこう大きい教室を会場にしているので1公演で約100名前後、のべ400~500名の方に観ていただいているはずです。
※今年は新型コロナウイルスの影響で、大東祭は中止となりました。
──将棋同好会の歴史についてはいかがでしょうか?
佐藤:調べてはみたものの、はっきりしたことはわかりませんでした。ただ、部室に昭和に活躍された大山康晴十五世名人のサイン色紙があるので、歴史は感じます。
──琴和道会はずいぶん古くから始まったと聞いています。
橋本:発足は1968(昭和43)年ですから、半世紀以上です。3代前の幹事長が中心となり調べた結果、今(2020年)から 2年前に50周年を迎えたことが判明しました。琴和道会に対する愛がとても強い先輩で(笑)、最初の部員の方まで訪ねて行かれました。
──大東祭のほかにも演奏会は行っていますか?
橋本:六月祭と大東祭がメインですが、新入生を歓迎する春や卒業記念の演奏会なども行います。学外では、毎年12月に板橋区立文化会館で開催される定期演奏会が大きなイベントで、今年も23日に予定していますがまだ確定はしていません。ほかに、ひな祭りの時季には附属の青桐幼稚園を訪問して演奏をしています。
──部活動を通して身についたものや新しい気づきはありますか?
大川:たとえばプロのお笑いの作品を観る際も、ネタの構成を意識するようになりました。「ここで伏線を張っているのか」とか「ここでオチをつけるのか」とか。視聴者の立場から、作り手(演者・裏方)の立場になったことで、観客は何を求めているのか、どのようにしたら楽しんでもらえるのかなど、今までしたことのない考え方ができるようになりました。
──将棋はどうでしょう。棋譜の研究とかもされていますか?
佐藤:部活ではあまりしませんが、大会前は必要に迫られて研究することもあります。
──たとえば藤井聡太二冠の報道にしても、「昼食に何を食べた」とか「恰好」とかワイドショー的な視点ばかりで、肝心の棋譜についてはなかなか伝えらえません。やはりルールとゲームの複雑性が高い壁になっているのでしょうか?
佐藤:ルールは大前提ですから、それこそが将棋という伝統文化の難しさかもしれません。馴染みのない漢字で書かれた駒も多くて、最初はとっつきにくい印象を持たれるかと思います。ただ、老若男女隔たりなく楽しめるという大きなメリットもあります。
──若干17歳の高校生が、お父さんほど年の離れたベテランを負かしてしまうわけですからね。
佐藤:はい。ですからいきなり本将棋に臨むのではなく、挟み将棋やドミノ崩しといった簡単な遊びを通して、駒にふれることから入っていくのもいいかと思います。
──橋本さんは部活を通して発見したことはありますか?
橋本:たとえばお筝だと、ふつうに弦を弾くだけではなくて、お筝自体を打楽器のように叩いたり、三味線でもバチで弦をこすりつけて「ギュルギュル」という音を出したり、自分がもともと想像していた優雅な音ではなく、激しい音を出す技法があることに驚きました。
──古典文化や芸能を習得する難しさと楽しさについてはどのように感じていますか?
橋本:箏、三味線、尺八による演奏や合奏は指揮者がいないため、皆で心を一つにして息を合わせなくてはなりません。個人でたくさん練習しても、いざ合奏練習をしてみると、最初はタイミングやリズムがずれてしまうことがよくあります。しかし、皆で曲の雰囲気や強弱、速さなどを話し合い、何度も何度も合奏練習をして、それぞれの楽器の音が重なり合って一つの曲になったときの感動は格別です。難しいと感じることは多々ありますが、それらを試行錯誤していく中で和楽器の奥深さや楽しさを見つけ出すことができます。
学科のくくりとは異なる部活動ならではの絆と連帯感
 大川楓佳さん(落語研究会)
大川楓佳さん(落語研究会)
──大川さんは事前のアンケートに「お笑いは人々に笑いを届けることと」といったメッセージを記されていますが、こんな時期だからこそ感じることもあるかと思います。
大川:エンターティンメントがないと生活に張りが生まれませんし、そもそも笑うって(人が生きるうえで)とても重要なことだと思います。自粛期間中に劇場でのライブやテレビ出演がままならない中、多くの芸人さんが動画配信しているのを目にし、やはり笑いは必要と身に染みて感じました。
──どんな事象でもネタに変えられるのが笑いの強みですものね。
大川:もちろんタブーやNGはありますが、舞台の上の表現は自由だと先輩からも言われます。ソーシャル・ディスタンスを逆に利用した新たなアイデアも模索できると思うので。
──最後に、部活動の楽しみ方やそれぞれの部活の紹介など、在校生や受験生へ向けたメッセージをお願いします。
大川:部活は学科よりも少人数ですし、同じ趣味嗜好の集まりなので親交を深めやすいと思います。とくに現在のような状況下では、SNSなどを通して部活動以外の相談もできるし、連帯感も生まれます。部活動の良さって、そんなところにもあると感じています。
橋本:和楽器の経験がなくても、私のように、大学で何か新しいことをしたい、と思っている人は気軽に挑戦してください。部員全員で力を合わせて一つの曲をつくり上げる、その楽しさを味わえるのも部活動ならではですから。
佐藤:将棋研究会はいい意味で“ユルい”サークルなので、規律や厳しさが苦手な人にはおすすめです。また、部員も個性豊かで面白い人が多いので、ぜひ見学に来てほしいです。
(了)