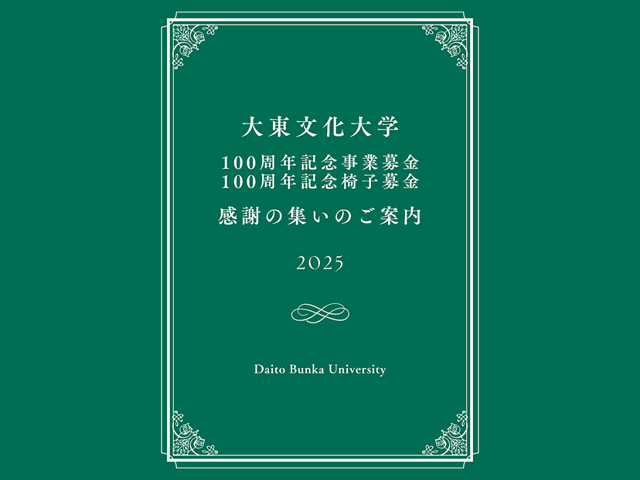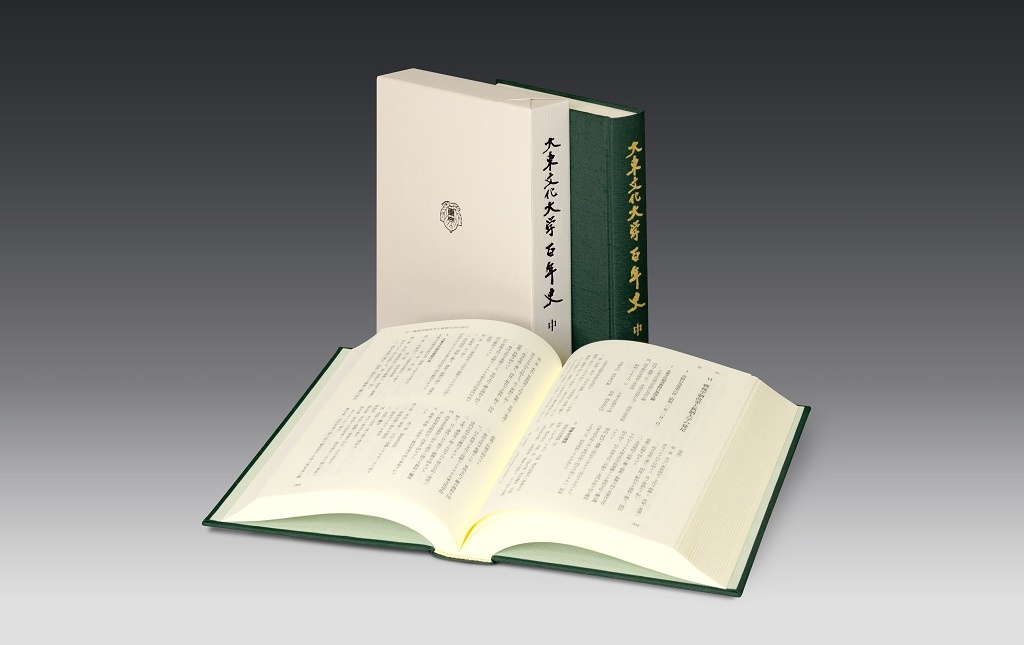教育その他
2020.12.23
地域の現場でリアルに学ぶ。政治学科「政治学インターンシップ」インタビュー①
以前レポートした政治学科の「政治学インターンシップ 」。こちらの科目はいずれも他学部他学科開放科目として全学部生が受講でき、福島研修のほかに、「東北(宮城・岩手)被災地研修」「登別での政策デザイン研修」「安全保障研修」「沖縄研修」という多様な地域でのフィールドワークが行われています。
様々に異なる「現場」に、様々な学部学科から集まる学生が触れる「政治学インターンシップ」。
その開講の意図や展望について政治学科の先生方に伺いました!
理論と現場が交差する、立体的な学問の場
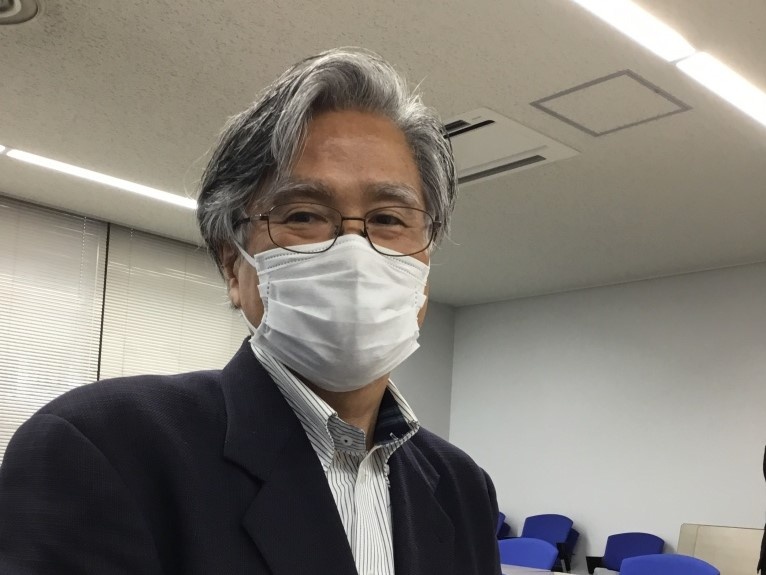 加藤法学部長
加藤法学部長
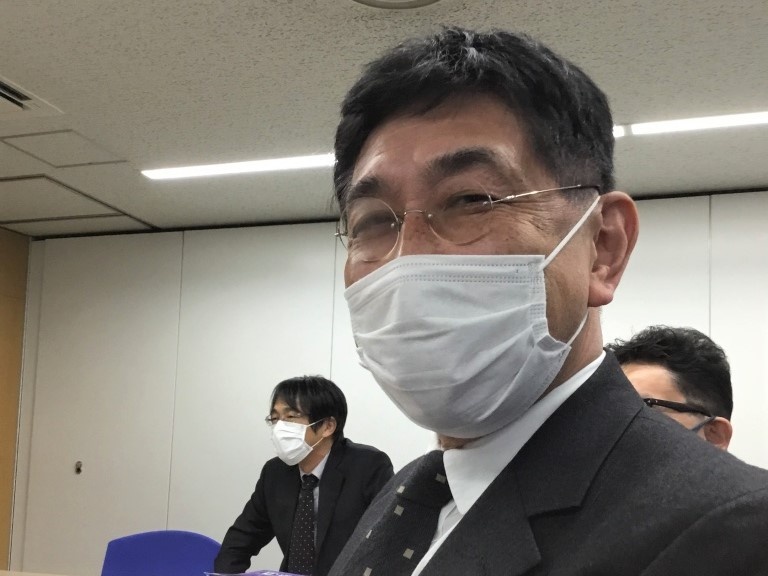 平尾政治学科主任
平尾政治学科主任
---さっそくですが、政治学科にとって、「政治学インターンシップ」はどのような科目ですか?
法学部長 加藤 普章 教授: ひょっとすると意外に思われるかもしれないのですが、政治学というのは元来、抽象的な学問です。
今我々が生きているこの社会では、多種多様な問題がありますが、これらの具体的な問題をそのまま取り上げるのではなく、そのような問題をいかに抽象的に政治現象として説明するか、というのが、政治学の学問的手法となります。
しかし、この抽象的な学問なり議論なりに至るそのスタートには、やはり実際に起こる政治的な問題や社会的な問題があるわけです。
実際の問題とかけ離れたところに学問があるわけではありません。将来社会で活躍する学生たちに、現場の話をいかに伝えていくかということも政治学科としてきちんと押さえておくべきことであろうと考えています。
政治学インターンシップは、座学としての学問に加え、「現場」からの視点、意見や立場の異なる「現場」の人々とのリアルな交流を通じて学生のみならず教員もまた学生とともに学ぶ、そんな科目となっています。
福島研修の例を挙げるならば、原発事故の問題に関してきちんと理解しようとするには、政治や社会のことだけではなく、理工系の素養も必要となります。
政治学科には物理学を専門とされている平尾先生がおられます。このことによってさらに「現場」を見る目が立体的なものになったと思います。
政治学科主任 平尾 淳一 教授: そうですね、原発についての問題を取り上げることで、政治学をエネルギー・環境といった側面から見直すことができるようになります。
また、このような世界共通の問題をそれぞれの地域で直に感じて学ぶことができるのが「政治学インターンシップ」の特徴であると思います。グローバルな問題をローカルに学ぶといったところでしょうか。
この研修に関連して福島を訪れた際、駅のコンコースに新エネルギーに関する展示がありました。現地では災害復興もさることながら将来を見据えた産業振興・地域振興に向けて動き出していることに気づき、「政治学インターンシップ」においても積極的に未来に向けた学びを志向する必要性を感じました。そしてここでの学びが就職という形でそれぞれの地域への貢献につながるように進められると良いと考えています。
学生と教員がともに「現場」に学ぶ。科目が生まれたきっかけは?
 武田教授
武田教授
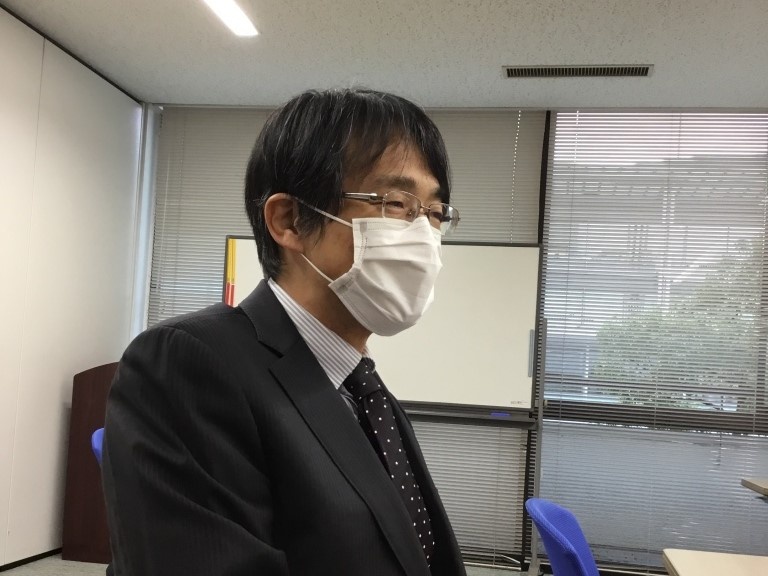 藤井准教授
藤井准教授
---先ほど、加藤学部長が「先生方もまた学生と共に学ぶ」とおっしゃいましたが、福島研修を中心になってご担当なさった武田先生から、この辺の実感というのはいかがでしょうか?
政治学科 武田 知己教授: 私は物理学に縁遠く、原発や原発事故に関連する物理の問題に関しては平尾先生に教わりながら進めてきたので、その意味でも本当に学生と共に学んだのですが(笑)、
実際、学問として抽象化されていない、現場の生の素材を扱うということは教員にとってもチャレンジングなことです。
11月に報告会を行った福島研修について言いますと、福島が3.11からどう動きながら復興を成し遂げていけるのか。これはまさに政治学が範疇とする動きですが、まだまだ渦中にあります。
様相が様々な社会状況によって変化する、そのダイナミズムの中で政治学を考えることは大変刺激になります。
----このような科目を設けたそもそものきっかけをお伺いして良いでしょうか?
政治学科 藤井 誠一郎准教授: 2017年の全学プロジェクト予算の公募採択事業に採択されたことですね。種となったのは私がもともとゼミ生を中心に行っていた取り組みです。手弁当で小規模にやっていたのですが、教育効果があるのは分かっていたため、もう少し広がりを持たせられたらいいなと思いまして、全学プロジェクト予算に応募しました。
採択をきっかけに、ゼミでの活動から学科の取り組みへ、さらにカリキュラムへの展開や他学部他学科開放科目へと徐々に拡大していきました。登別、沖縄、宮城、福島…各地で研修にご協力くださる学外の方々、学部長をはじめとした、学内の教職員の皆さんのサポートのお蔭でここまで育てることができたと思っています。
開始当初から今まで、学生を大学の外に連れて行って、きちんと政策なり課題なりの現場を見せてあげることの意義と難しさというのを、一貫して感じているところです。
----第2回につづく
☆次回以降は各研修の特徴、そして「政治学インターンシップ」の今後の展望についてお伺いします。どうぞお楽しみに!
☆「政治学インターンシップ」 は政治学科の科目で他学部他学科開放科目となっています。
2021年度は(1)東北(宮城・岩手)被災地研修、(2)福島研修、(3)登別での政策デザイン研修(2年生向け)、同(3年生向け)、(4)安全保障研修(希望者は沖縄研修も可能)、(5)沖縄研修を行います。現実の問題に取り組むジャーナリストや公務員などを志望する学生、また将来教員として社会科・公民などを教えたい学生の参加を特に歓迎します!
興味のある本学の学生はシラバスをご参照ください。また、授業内容に関するお問い合わせは法学部事務室までどうぞ。