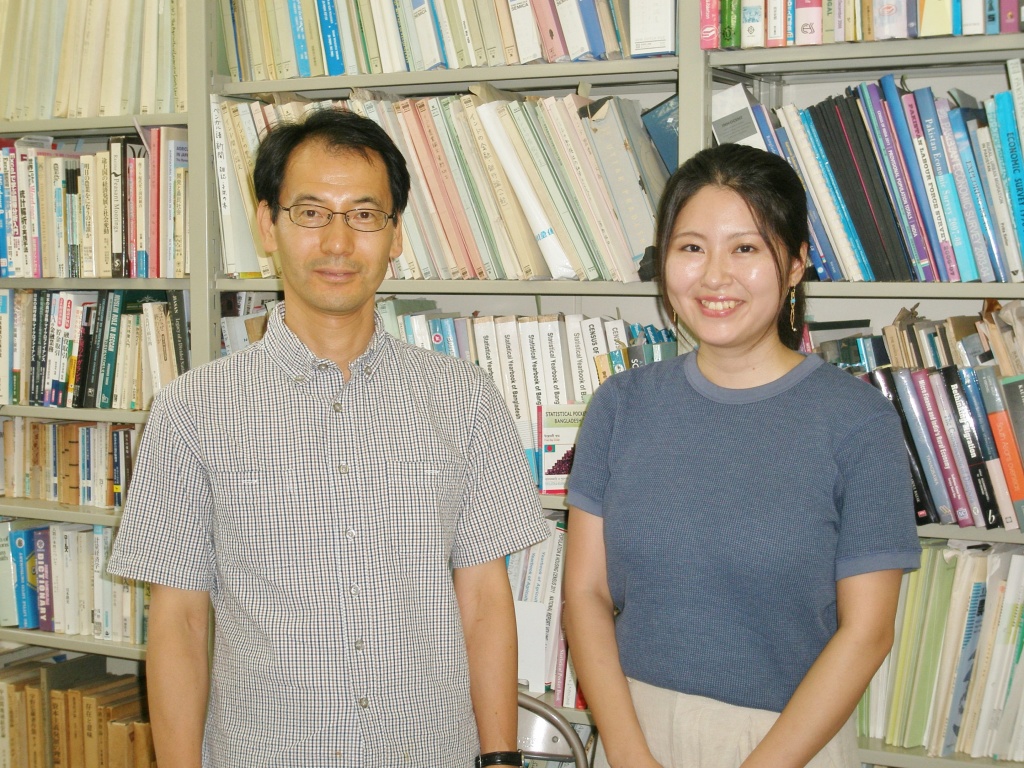2014年度に国際関係学部を卒業した高木郁絵さんは、2016年6月に、日本国際協力機構(JICA)の青年海外協力隊(JV)として、ネパールに派遣され、2年間の任務を終えこのほど帰国しました。
8月2日、ゼミの須田敏彦先生への帰国報告のために東松山キャンパスを訪れた高木さんに、新里学部長が、JVのOBである国際関係学部事務室の山田岳さんとともに、二年間のネパールでの体験について伺いました。
◆高木さんが、JVを志したきっかけは何ですか?
高校生の頃から、国際協力に関心がありました。学部時代はインド留学を体験し、卒業後はNGOで働くことも考えていました。しかし、NGOには実務経験が応募資格となっているところも多く、諦めかけていました。
そんなときに友人からJICAの青年海外協力隊を勧められ、応募を決めました。第一希望であり、学部での南アジアの学びが活かせるネパールに派遣されたことは幸運でした。
◆高木さんの任地について教えてください。
パルパ郡タンセン市(ルンビニとポカラの中間)に居を定め、そこからジープで3時間半ほど離れた村が活動の拠点でした。数日間は村に滞在し、1週間か2週間に一度タンセン市に戻る生活をしていました。
言葉はネパール語で、ほとんどの人がヒンドゥー教を信仰しています。ダルバート(豆+米)が主食です。農業や牧畜が主産業であり、とりわけ女性は真面目で、朝早くから夜までよく働いている姿が印象的です。外国人への敬意を忘れず、しかし、とても人懐っこく、何度も家に招いてもらいました。
◆協力隊として、この2年間に主にどのような活動をされたのですか?
派遣されたのはネパール政府が管轄する土壌保全事務所。「SABIHAA」プロジェクトを推進する組織です。SABIHAAとは、Saamudaayik Bikaas Tathaa Hariyaalii Aayojanaa(ネパール語で村落振興・森林保全を意味します)。地方行政の強化を通じ、コミュニティ・リソースの管理やコミュニティ開発のすべてのステップに住民の人々が参加することを促進するメカニズムです。森林保全のみならず、住民の生計向上、エンパワーメント等との両立を目標とします。JICAは1990年代から複数のプロジェクト及びボランティア派遣を通してこのSABIHAAモデルの普及・強化を推進してきました。「SABIHAA」の支援グループの一つに村の女性たちで編成されるパワーグループがあり、わたしは、その女性グループを主として支援しました。
もっとも大きな成果として、女性たちの収入向上を目的とした「蜜蝋キャンドル」の事業があります。当初、箒草の栽培による収入向上を目指していたのですが、1kg=20円ほどの収入しか得られませんでした。フィールドワークを重ねた結果、養蜂に着眼し、蜂蜜をとったあとの絞り糟から「蜜蝋キャンドル」を作る事業を提案し、事業化しました。
たいへんな作業でしたが、村の女性たちと力を合わせ、蜜蝋キャンドルはもとより包剤のデザインと作成から販路の開拓まですべてかかわりました。
わたしたちの蜜蝋キャンドルには「PRAYASH」(プラヤース)とネパール語の名前をつけました。「Try」という意味です。カトマンズで、1個500円で販売し、30個が完売したこともあります。今後もこの事業が発展し、収入向上に益することを願っています。
◆ネパールでの活動中、もっとも印象に残っていることはどんなことですか?
「OKBaji」こと岸見一雅さんとの出会いです。フィールドワークにもご一緒させていただき、いろいろなお話を伺いました。また、地元の人々の信頼が篤く、子供でも大人でもどんな人にも分け隔てのない態度で接する姿に感動しました。さらに、78歳の高齢とは思えない健脚にも圧倒され続けました。
◆高木さんの今後の活動について教えてください?
明確なビジョンはまだ描けていませんが、ネパールの会社で働くことも考えています。将来は、小さくてもいいので、ネパールとかかわりのある事業を起業したいとも考えています。
体験報告会へ
後期のチュートリアルの授業で、坂下さんと高木さんをお招きして学部独自のJV講演会を開催することになりました。
ところで、11月に開催される第21回ALSCのテーマは「2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて私たちにとっての異文化理解とは」。二年間、アフリカやアジア地域で、現地の人々との協働を経験した卒業生にも、異文化理解について語ってもらえればと思います。