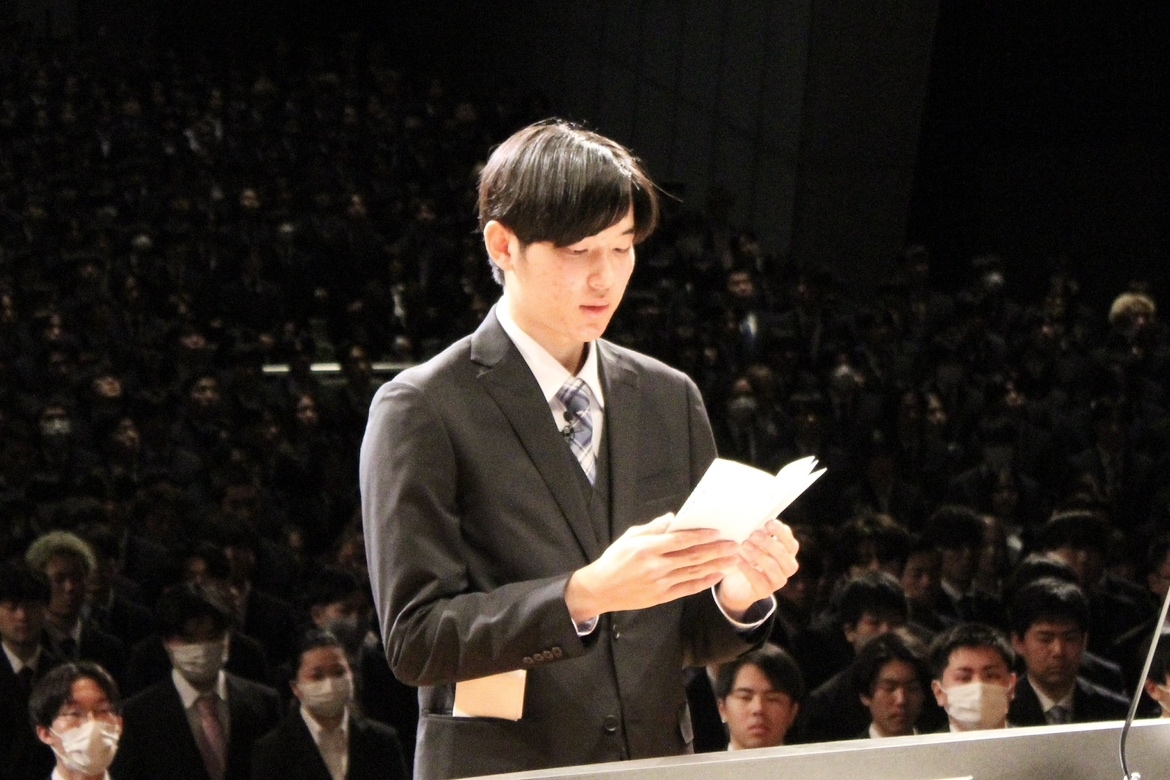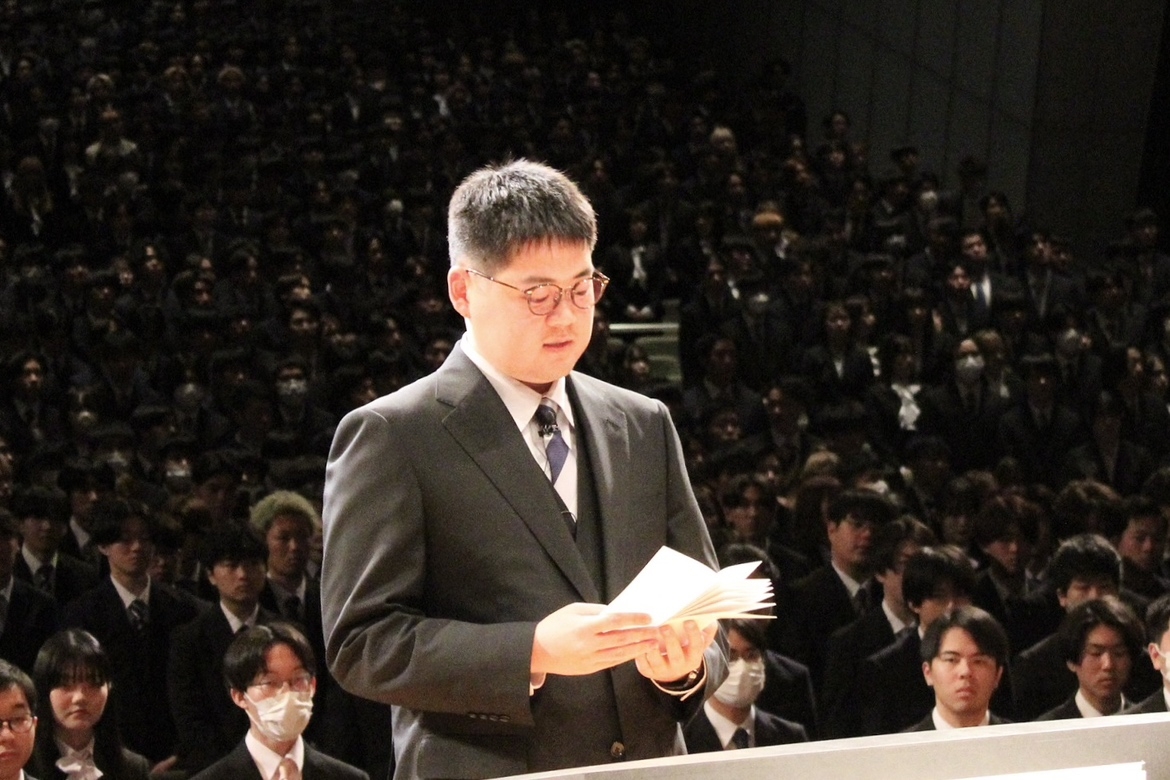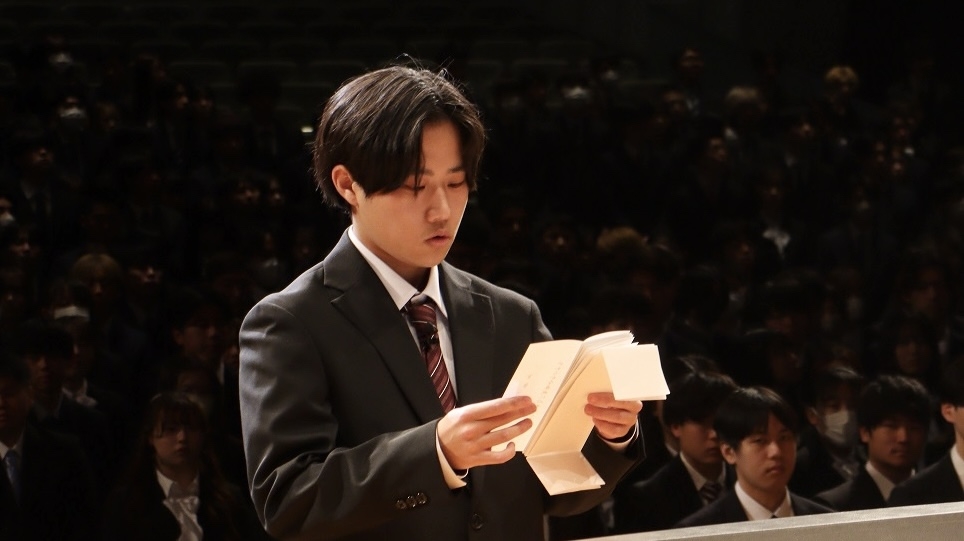2025年度入学式が4月4日、東京都千代田区有楽町の東京国際フォーラム・ホールAで 挙行され、8学部20学科6研究科3,416人が入学した。
学部別の入学者数は文学部731人、経済学部426人、外国語学部412人、法学部486人、国際関係学部217人、経営学部434人、スポーツ・健康科学部416人、社会学部236人。
研究科別の入学者数は文学研究科19人、経済学研究科4人、外国語学研究科8人、アジア地域研究科2人、経営学研究科5人、スポーツ・健康科学研究科13人(博士課程前期課程・修士課程)。文学研究科3人、外国語学研究科2人、アジア地域研究科1 人、経営学研究科1人(博士課程後期課程)。
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。そして、新入生のご家族や関係者の皆様にお祝いを申し上げます。また、心から感謝の意を表します。ご令息、ご令嬢が、今日ここに新たな一歩を踏み出すステージへ進むことができたのも、皆様の支えと励ましがあったからです。これからも皆様の献身的なサポートが、学生たちが成長するための大きな原動力になるに違いありません。
さて、大東文化大学は、皆さんが夢に向かって進むための支援と協力を惜しむことなく、皆さん一人一人の成功を心から願っています。大いに学び、逞しく成長し、世界に羽ばたいて活躍される皆さんの雄姿を私たち教職員は期待しています。そのために、私達は、常に尽力して参ります。これからの四年間の旅路を共に歩んで参りましょう。
本学は一昨年度創立百周年を迎えました。新入生の皆さんは、次の百年に向けて新たなる大東文化大学の歴史を創り上げるために入学をされたと言っても過言ではありません。
皆さんが、新しい歴史の担い手になるために、温故知新という言葉が示すが如く、先ずは、本学の沿革や建学の精神について、簡単にご紹介をさせて戴きたいと思います。
大東文化大学の前身である大東文化学院は、1923年、帝国議会の決議によって創設された大東文化協会によって設置されました。奇しくも、それは大正12年。この年9月1日には、関東大震災が発生したことは周知のとおりです。そのような大激動の社会において、本学は9月20日に開学をする運びとなったのです。
また、その決議とは、東洋の文化を基礎として西洋の文化を吸収し、東西文化を融合して新しい文化の創造を図ろうとする有識者の提案によるものでした。明治維新以降、日本社会は、近代化を求めてひたすら西洋化を追い求めました。一方、そのような近代化への急激な社会変革に対して、一定の危惧感も生まれたことは確かです。
本学の開学の必要性を示した多くの有識者が日本を憂い「自国の文化やアジアの文化を知り、ゆるぎないアイデンティティに基づいて西洋文化の良さを吸収していく」ことの意義を唱えたのは、まさにそのためだとも言えるでしょう。現代に通じる国際社会の規範ともなる考え方です。そして、この考え方に基づいた活動は、本学においてはすでに創立当時からはじまっていたのです。大東文化学園は、東西文化の融合のあり方を説いたこの考え方を、建学の精神としているのです。多様性の重要性を開学当初から訴え続けているということは、本学の素晴らしい特徴とも言えましょう。
ところで、皆さんは未来についてどのように考え、どのように描こうとされていますか。皆さんの門出に際して、良い未来を築くための重要な思考について少し触れることにしましょう。
先ずは、何といっても有意な目標設定が重要となります。エドウィン・ロック(Edwin A. Locke)が、1968年に「目標設定理論」を提唱しました。具体的で挑戦的な目標を設定することが、動機付けとパフォーマンスの向上に繋がるとロックは説いています。皆さんは、将来の夢を抱いて入学式を迎えられていると思います。その夢への工程表を期限付きで具体的に描いてみてください。それだけでも、やる気が湧いてきて夢へ一歩も二歩も近づいていくはずです。
次に、ノーマン・ガーメジー(Norman Garmezy)あるいはマイケル・ラター(Michael Rutter)らが提唱した「レジリエンス理論」についてもご紹介をしたいと思います。一言で言ってしまえば、「柔軟性と適応力」の涵養が、悲観的にならずに自分の掲げた目標に近づく一方法であるということです。例えば、友達がサークルの会議に遅刻した場合、ある人は「やる気がない」と怒りを感じるかもしれません。また、別の人は「やることが多くて忙しいのかもしれない」と心配するかもしれません。皆さんは、どちらのタイプでしょうか。同じ出来事でも、解釈の仕方によって感情や行動が変わることは、皆さんも理解戴けると思いますが、できるだけポジティブな解釈をすることを心がけることで、「レジリエンス」を高めることができるというわけです。怒りの感情が助長されることによって、自己の動機水準も下がってしまいます。先の見えない社会、何が起こるか分からない未来にとって「レジリエンス」を高めることは実に有益です。
そして、アルバート・バンデューラ(Albert Bandura)が、1977年に提唱した「社会的学習理論」についてもこれからの4年間の中で非常に重要な理論の一つでしょう。「モデリング理論」などとも言っていますが、例えば、皆さんが、サークルに入部した時に、模範となる先輩のサークル活動の運営の仕方を観察し、それを模倣することで、容易にスキルを習得することが可能になります。発表における、先輩のサークル活動でのプレゼンテーションを見て学ぶことなどは良い例でしょう。良い部分を参考にし、自分のプレゼンテーションに応用することができれば、皆さんのプレゼンテーションスキルは飛躍的に向上するはずです。皆さんが目標としたい社会モデルを見つけ出し、模倣をすることは本当に大切なことです。
そして、最後になりますが、「フロー体験を意識する」ことも忘れてはなりません。これは、マーティン・セリグマン(Martin Seligman)らのポジティブ心理学(Positive Psychology)の要素の一つではありますが、自分が没頭できる活動を見つけ、それに時間を割くようにすることもこの4年間の中で、夢へ向かう際の動機水準を維持していくためには必要です。絵を描く、楽器を演奏する、スポーツをする、ゲームに興じるなど、自分が楽しめる活動を選んで、意識的にフロー体験を作り出してください。充実感を得ることで、ポジティブな思考が助長されます。ポジティブな心構えを持つことで、皆さんが、困難を乗り越えやすくなり、より充実した人生を送ることができるわけです。
「具体的で有意な目標」を設定して下さい。「柔軟で言わば楽観的な思考」を持って下さい。「目標となる社会モデルを見つけ出し、先ずは真似る」ところから始めて下さい。そして「何でも構いません。没頭できることを見つけ出し、充実感を味わって」ください。ポジティブな思考は、夢に向かう原動力になるはずです。
さあ、今日この日から、皆さん一人一人が、大東文化大学の一員となります。大学生活でしか経験できないことがたくさんあります。人生の中で最も美しい、最も有意義な時間、それが大学生活です。これからの一瞬、一瞬を大切に過ごして下さい。
最後になりますが、新入生の皆さんの未来は、無限の可能性に満ちていることを改めて皆さん自身で感じて下さい。そして、この学び舎で自分自身を成長させ、社会に貢献できる人材となることを期待しています。
新入生の皆様、学部、大学院へのご入学、誠におめでとうございます。新入生の皆様はもちろん、このたび入学される新入生を育て、支えてこられたご家族・ご親族の皆様も、たいへんお喜びのことと存じます。心からお祝いを申し上げます。
また、新入生の門出を共に祝うため、お忙しい中を縫ってご出席いただきましたご来賓の皆様、誠にありがとうございます。
新型コロナの鎮静により、数年ぶりに以前と同じ姿での入学式で皆様をお迎えできますこと、大変喜ばしく思っております。
皆様は本日、新たな学びのステージに第一歩を踏み出しました。ここに到るまで、多くの努力をなされたことと存じます。保護者、先生を始め多くの方の支えがあったことと存じます。
学園として、これからの数年間が有意義で充実したものとなるよう、そして皆さんが夢に向かって進むためのサポートを最大限提供したいと思っております。
さて、せっかくの機会ですので、ここで特に大学に入学された方に向けて、3つのことを申し上げさせていただきたいと思います。
まず一つ目ですが、大学における学びはこれまでとはかなり性格が違うものになるということです。これまでの学びとはかなり異なるものになると思います。大学院でも程度は違えど異なるものがあると思います。
高校までは、どちらかと言えば知識を得ることに重きがあったのではないかと思います。大学では手取り足取り教えてもらうというのではなく、自分で学んでいく、方向、深さを切り開いていくことになるはずです。自律的な学びの場とでもいいましょうか。大学は、確立した知識を学ぶだけの場所ではないのです。
根拠、エビデンスを重視し、確認をして自らの頭で考えることが重要となります。検索やAI等で手っ取り早く参考情報を仕入れて結論を得る、形にするのではなく、原典に当たり、確認し、自分の頭で考え、自分の言葉でその考えを伝える、時に仲間とで議論をし、一定の考えに至る、そうしたプロセスは大変重要です。学びをデザインするということの喜びを同時に感じていただきたいと思います。
二つ目は、大学は最高学府ですので、多様な知に大いに触れていただきたいと思いますが、それだけではなく、できる限り多くの友人、先輩、先生と接していただきたいということです。そして「多くの様々な違い」に触れていただきたい、「違い」を感じ取っていただきたいと思います。
おそらく皆様はこれまでの行動範囲よりも広い範囲から集まる方々と接することになるはずです。その方々との交流からこれまで知らなかった考え方、文化、習慣に出会うはずです。言葉の違いもあるでしょう。大東文化学園は国内からも様々な地域、そして国外からも多くの留学生を迎えております。これまで慣れ親しんだものや考え方とは違いがあることに驚くこともあるかもしれません。これまで当たり前と思っていたのとは違う習慣や感覚に触れることでしょう。その違いを是非受け止め、尊重していただきたいと思います。
少し古い言葉になりますが、今はVUCAの時代といわれています。VOLATILITY(変動)、UNCERTAINITY(不確実)、COMPLEXITY(複雑)、AMBIGUITY(あいまい)の4つの文字の頭文字をとった言葉です。持続的に環境が変化することはわかっていても、どのように変化するかを予め正確に予測することが極めて難しい時代になってきていることを意味しています。技術、ルール、常識がどんどん変化してきているのは皆さんも日々感じていると思います。このような時代では、進むべき道があらかじめしっかり見えているわけではありません。
こうした予測がつきにくい時代を生き抜くには、多様なものの見方、価値観を受け入れる力が重要になります。そのためにはまず、様々な属性やバックグラウンドを持つ人の多角的な物の見方、多様性があることを知っていただきたいと思います。その上でそのことを受け入れ、理解することができれば多様なニーズの存在に気づかされ、世の中の変化を敏感に感じ取れることになるはずです。だからこそ、今組織の中では、また国レベルでもダイバーシテイすなわち多様性が推進されているのです。
大東文化学園は、学長の告示にもあった通り、建学の精神において、今を先取りして、ダイバーシテイに早くから着目をし、それを育み、推進してきました。異なる文化への理解力・共感力の養成を本学園はそのミッションとしております。
是非皆さんも様々な違いを尊重し、そこから学ぶ姿勢をもつ、柔らかな、しなやかな考え方ができる存在になっていただきたいと思います。
最後に申し上げたいのは、これからの数年間においても、いろいろな挑戦をしていただきたい、そして失敗もあると思いますが、いろいろ挑戦をしてみるという姿勢をお持ちいただきたい、ということです。
ある方がおっしゃったことなのですが、挑戦して成功するのは素晴らしい、でも挑戦しないで失敗しないというのはいかがなものか、失敗しても挑戦する人、成功するまで挑戦をあきらめない人は素晴らしいのだと。
誰しもできたら失敗はしたくないものです。でも、失敗から学べることはたくさんあります。失敗した後が大切なのだと思います。そこで失敗してしまって辛かった、嫌だった、と言って忘れてしまうことも時には必要かもしれませんが、どこかで立ち向かってほしいのです。「せっかく失敗したのだから」と失敗に至った原因を振り返って、そこから学ぶ姿勢をもち続けていただけたら、皆さんは成長、進化した自分に出会えるはずです。
なお、一応申し上げておきますが、また、言わずもがなですが、ここで言う挑戦は、法律違反に当たること等違法なものは含みません。それは当然NGです。
最後にもう一言申し上げます。皆様お一人お一人にとって、本学園で過ごす時間が素晴らしいものとなりますように、多くの人と出会い、多様な知に触れ、その後の人生にとっても大切な時間となることを願っております。
のびのびと大学生活、大学院生活を楽しんでください。
皆様のこれからの数年間が実り多いものとなりますことをお祈りして私からの祝辞といたします。
新入生宣誓(現代経済学科 武政 和馬さん)
厳しい寒さも落ち着き、春の訪れを感じる今日この日に、こうして大東文化大学の入学式を迎えられたことを新入生一同大変嬉しく思います。
新入生宣誓(経営学研究科経営学専攻 粂川 辰徳さん)
厳しい冬の寒冷を越え、自然の新たなる生命の息吹を感じながら、今日私達は大東文化大学大学院の学生となることができ、大きな喜びを感じております。
今、世界は激動のさなかにあります。AI(人工知能)は、まさに日進月歩で進化を遂げていて、これまで人間が行ってきた業務を代替することも現実味を帯びてきました。ウクライナやパレスチナでは戦闘が続き、国際社会のキーワードは「グローバル化」から「分断」へと変わりつつあります。こうした情勢下で「経済安全保障」が提言され、九州や北海道に半導体の生産拠点を構えようとする動きが活発なものになっています。
最後になりますが、本学の大学院での研究の機会を頂き、大変光栄に存じます。私達の前に広がる研究者としての道には、多くの困難もあることでしょう。しかし、そのような困難すらも糧に邁進してまいります。これまで支えてくださった多くの方々、またこれから出会う人々への感謝を常に忘れることなく、今まで以上に有意義な研究生活を送ることをお誓い申し上げます。
新入生宣誓(歴史文化学科 原口 瑞都さん)
やわらかな春風に心華やぐ季節となったこの良き日に、100年以上の歴史を持つ大東文化大学に入学できることを新入生一同大変嬉しく思います。
新入生宣誓(文学研究科日本文学専攻 陳 宇軒さん)
春の訪れを感じながら、新たな学びの場へと歩みを進める今日、私たちは大東文化大学大学院の学生として一歩を踏み出せたことに深い感謝と喜びを感じております。