姓名論雑考:モンゴル人
李妍淑
革命がかえた姓差別
モンゴル人の社会は、古くはオボクと呼ばれる父系氏族の単位によって組織されていた。そして、同じオボクの出身者は相互の婚姻を禁じた族外婚制であったため、血縁に関する知識は非常に重要であった。だから、何々オボクの誰々といういい方をしていたが、通常はその人の名をそのまま呼んでいた。1921年の革命は、こうした出身により区別を廃止したから、人を呼ぶ呼び方は、日本でいう「呼びすて」以外にはないのである。
しかし同じ名があまりにも多いときは、それらを区別するために、父親の名を冠し「誰々の(子)誰々」という呼び方をするのである。今ここにツェレンという男の子がいて、その父がバートルなら、バートリーン・ツェレンというように呼ぶのである。しかしそれは、本を書いたときや公式の場以外ではめったに使われることがない。
時代の波
さて、現代のモンゴル人にはどんな名が多いか。男の子ならバートル(英雄)、それにいろいろな形容詞をかぶせたフレルバートル(青銅の英雄)、チョローンバートル(石の英雄)などがある。女の子ならツェツェグ(花)だけの場合もあれば、それにいろいろと飾りをつけてムンフツェツェグ(永遠の花=エーデルワイスのこと)、ナランツェツェグ(太陽の花=ヒマワリ)などとする。オヨーン(智慧)、トヤー(輝き)、ゲレル(光)、また両方をくっつけたゲレルトヤーなどもよくある。
これらは純粋にモンゴル語の名前であるが、仏教の信仰のあつい民族だから、それにちなんだチベット名をそのままつけたものも多い。例えばダムディンだが、これは馬頭観音のことで、さらにスレン(守護)をつけたダムディンスレン、またナツァグ(宇宙)とドルジ(金剛)をあわせたナツァグドルジも多い。女はドルマー(女神の名)から派生したツェレン(長寿)ドルマーさんにはたびたび出会う。
サンスクリト語の名も、もちろんチベット語とならんでたくさん用いられる。例えば、今の大統領オチルバト(1991年当時:web編注)のオチルは、サンスクリト語のワジラ(金剛)が変形したもので、バトは純モンゴル語で「堅固」という意味である。バダム(蓮花)はサンスクリト語のパドマが変形したもので、バダムオチルというありがたい名前の人もいる。
仏教が言語や民族の境界を越えて人々に共通の名を与えているのは、ちょうど西洋におけるキリスト教の場合と同様である。つまり、ヨハネはドイツ語に入ってヨーハン、英語でジョン、フランス語でジャン、イタリア語でジョヴァンニ、ロシア語でイワンとなるようなものである。形は言語ごとに違っても、同じ使徒のことが考えられているのである。
名づけにはやはり時代の影響というものが強く現れ、ソビエトとの関係が深かった最近まで、女にはニーナとかターニャ、男にもミハイール、コマロフなどというロシア人名が現れた。またカンボルトなどという名は、モンゴル語ながら時代を感じさせる。カンは中国語の「鋼」に由来し、ボルドも同じ意味のモンゴル語だが、これはどうもスターリンにあやかったのではないかと思われる。スタールというロシア語は英語のスティールと同じ起源の「鋼鉄」という意味だからである。ペレストロイカの進行とともに、今後はいっそうモンゴル風、仏教風の名が好まれるだろうと考えられる。
名のつけ方のおおらかさ
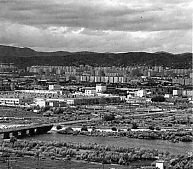
おもしろいのは、そのものずばり、動物の名をつけたもので、バーブガイ(クマ)、ミンジ(ビーバー)、ハリオーン(カワウソ)などはそれほど珍しくなく、ノホイフー(犬むすこ)なんていうのもある。
民族学的におもしろいのはオトゴンフー(末の息子)というもので、この子が最後だという意味で「末子」などとつける日本の風習と似ている。
人間であるのにフンビシ(人でない)などとつけるのは、魔物の注意を外らそうとするものと思われるし、またエネビシ(これじゃない)などという名も同様の意図があるのだろう。
よくある名で、おやと思うのはネルグイという名である。文字通り「名なし」という意味なのだが、自己紹介などして「私の名は名なしです」などということになるから、とてもユーモラスな感じがする。子供が生まれたとき、親がいないとか、旅にでて不在だったりして、しばらく名前をつけないでほっておくとこうなってしまうという。こうした名の持ち主が、それでは惨めな生まれ方、育ち方をしたかといえば必ずしもそうでないようだ。ずいぶん有名な人の子にもこういう名の人がいるから不思議である。
モンゴル人の名には、われわれ漢字使用の農耕社会にはみられない、おおらかさと明るさが感じられる。