市・市場:在日朝鮮人市場―荒川区・三河島の例から―
大野祐二
1.はじめに
通常、「朝鮮人市場」という言葉からどのようなイメージを我々は抱くのであろうか。私が個人的に思い浮かぶものとして、大阪の生野区にある御幸之森商品街が最近「コリアンロード」として整備された例や、川崎市でも「コリアタウン」が構想され、この地域の韓国・朝鮮関係の店や施設が記された地図などが配布されているとのことだ。このように大掛かりで地域的なものではなくても、在日韓国・朝鮮人が多く在住しているところにはチマチョゴリなどを扱う民族衣装店やキムチの専門店、焼き肉店などがある。ここで紹介する例は、荒川区の日暮里にある、通称「朝鮮市場」であるが、6軒ほどの店一食料品店と民族衣装店、美容院など一が軒を連ねた小さな「市場」であり、戦後間もなくできて現在に至ったものである。また、三河島駅周辺にも韓国・朝鮮関係の店や施設が30~40近く点在していて、メディアの中でも「在日韓国・朝鮮人が多く住む町」として紹介されてはいるが(1)、先に触れた大阪や川崎のような形での展開はこれまでに見られない。
以下、限られた紙面の中ではあるが、先ずは簡単に荒川の在日韓国・朝鮮人社会について概観してから、この小さな「市場」がどのように成立して現在に至ったり、またそこでどのようなものが売られ、どのような人々が働いているのかなどを中心に、この朝鮮市場をめぐる《内》と《外》を描写してみよう。
2.荒川区の在日韓国・朝鮮人社会
常磐線の三河島駅(山手線の日暮里駅からでも徒歩で15分程度)を中心として、荒川区には現在約6500人の「在日韓国・朝鮮人」が生活している(2)。その中でも、韓国最南端の島である済州島からの人々がその半数以上を占め、更にその中でも高内里(コネリ)という済州島北西部にあるムラ出身の人々が多く在住している(3)。荒川区全体の人口比率では、4%に過ぎないが、三河島駅周辺に集中しているためか、実際には数字以上の印象を与えているようだ。いつ頃から、荒川区の三河島周辺に済州島の人々が住み始めたのかを知る資料は非常に少ないが、高内里出身者で組織されている在日本高内里親睦会の名簿によれば、1919年にこの村の出身者が荒川に来ていることが記されている。よって、1920年頃からこの地域に済州島の人々が住み始めたとみることができよう。済州島からの移住の背景は様々であろうが、植民地時代で終わる事なく、4・3事件や朝鮮動乱後から1965年の日韓条約の問にもかなりの人が来ているようであり、最近においては韓国で1989年に海外渡航が自由化されたこともあって、ここ数年三河島駅周辺にはハングル文字の看板をかけた食料品店、食堂、焼き肉屋から美容院、ビデオショップまでが開業しただけでなく、韓国からのキリスト教教会や仏教寺院もでき、そしてムーダンやシンバンまでもが活躍している。つまり、「済州島」と「荒川」との間には、70年以上にわたって人々の行き来が続いており、現在も進行中とみることができるわけだ。
【図1:荒川区における在日韓国・朝鮮人の住居(1950年)】
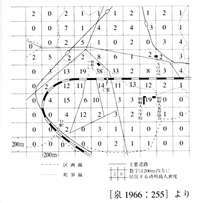 上の地図は1950年における三河島周辺の済州島出身者の居住密度を示すものであるが、私の印象では基本的に現在においても大きな変化はみられないように思われる。また、戦前から三河島を知る一世の場合、その多くは大阪や下関などでの生活を経てから、荒川に来ているようであり、70年間にわたる「済州島」と「荒川」間の行き来にだけでなく、他の移民社会と同様に荒川の在日韓国・朝鮮人社会の形成・展開においても、血縁的・地縁的な関係が重要であったことは十分に予想できる。
上の地図は1950年における三河島周辺の済州島出身者の居住密度を示すものであるが、私の印象では基本的に現在においても大きな変化はみられないように思われる。また、戦前から三河島を知る一世の場合、その多くは大阪や下関などでの生活を経てから、荒川に来ているようであり、70年間にわたる「済州島」と「荒川」間の行き来にだけでなく、他の移民社会と同様に荒川の在日韓国・朝鮮人社会の形成・展開においても、血縁的・地縁的な関係が重要であったことは十分に予想できる。
本稿で対象とするのは食料品や衣服類を売る店から成る「朝鮮市場」(図1で朝鮮人マーケットと記されている)が、荒川区在住の済州島出身者の職業構成(表1参照)から見れば、このような職業はごく少数派である。また、一世の職業としては、これまで土工・人夫が多いとされていたが、済州島出身者の場合にはあまり当てはまらず、1950年の資料ではゴム加工やミシン加工が目立って多いことが分かる。現在においては二世・三世が中心になり職業も多様化しているが、そのような技術を生かしてビニールの加工業やカバンの縫製業などが見受けられる。
| 職種 | 男 | 女 | 職種 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴム加工 | 26 | 1 | 露店商 | 1 | |
| ミシン加工 | 23 | 11 | 無職 | 5 | |
| 古物 | 2 | 洋裁 | 1 | ||
| 会社員 | 2 | 会社事務員 | 3 | ||
| 革靴製造 | 2 | 防績工 | 5 | ||
| 朝鮮服店 | 1 | 靴工 | 1 | ||
| 洋服店 | 1 | 裁縫 | 1 | ||
| ロウソク | 1 | 電気工 | 1 | ||
| 石鹸 | 1 | サーカス従業員 | 1 | ||
| アメ製造 | 1 | 海女 | 1 | ||
| 運送業 | 1 |
[泉1966:255]より
さて、東京の荒川という場所に形成された小さな「朝鮮市場」であるが、それを取り巻く三河島はメディアの中では下町として紹介されることがあるものの、大正初期あたりまでは正に東京の周辺部であり、関東大震災後に人口が増加し、町工場も増えたが、その多くは戦災で焼けるなど、入れ替わり、または流動の激しい「地域」であり、更に戦後50年が経過している訳である。本来なら、朝鮮市場を取り巻く日本社会の諸側面についても詳しく触れるべきであろうが、ここではそのような余裕はないので割愛する。
3.《市場》を構成する商店
次に、現在6軒から成る、「小さな朝鮮市場」にあるそれぞれの店について、簡単に記述してみることにしよう。先ずは、この市場がどのように成り立ったのかを、在日一世であるKさんの記憶を元に再構成してから、市場の中の《ヒト》と《モノ》について見て行くことにする。
3-1《市場》の成り立ちと展開
この朝鮮市場は、済州島で生まれ、大阪で暮らした後に三河島へ来た在日一世のKさん(76)が小さな「乾物屋」を構えたのがその始まりである。済州島の南部の村で生まれたKさんは7歳のときに両親に連れられて、1927年に大阪に来ている。当時、両親はゴムサンダルの工場で働いていたと言う(その後、11歳のときに済州島に戻り、19歳のときに再度大阪へ、そして20歳のとき故郷へ戻り、終戦の年の3月に再度大阪へ来て結婚と言うように、戦前は何度も大阪と済州島の間を行き来している)。
終戦後、3年間大阪にいたが商売に見切りをつけて、所有していた家を当時のお金で約9万5000円で売り、そのお金を元にして三河島にいたオルケ(兄嫁)を頼って、上京したのが昭和24年のことであった。彼女が現在の場所で商売を始めたのは昭和25年であるが、その頃は日本人が経営する、所謂「一杯飲み屋」があり、周りはバラックのような家であったそうだ。水道にしても、3ヵ所に井戸があり共同で使っていたと言う。彼女は取り敢えずその横に3万8,000円で買った小さな空間で、現在のような食肉などではなく、乾物屋を構えて商売をスタートした。彼女が、商売を初めて数年後に民族衣装店(現在のC店)がKさんの店より更に奥に入ったところで商売を始め、その後間もなくして魚を扱うA店ができ、B店もKさんの店で働いていた夫婦が独立して「乾物屋」として商売を開始したとのことであった。そして、韓国食品を扱うE店と美容院のF店は、3~4年前にできたとのことであった。つまり、Kさんの話からすると現在の朝鮮市場は、戦後(彼らの言葉では解放後)20年のうちにできたA店からD店までの4店と、最近できたE店とF店から構成されていて、戦前からあるわけでも、戦後一遍にできた訳でもなく、一軒一軒と増えて来たのである。
そして、次節で見るように、現在A店は魚ではなく食料品と焼き肉屋を経営していたり、B店も乾物屋から食肉と韓国食品を中心とした店になり、世代交代もしている。また、C店にしても、1962年に店と商品が合わせて売られ、更には昨年また新たな人に売られるなど、店の主人が3度代わっている。このように、売られる品物も変わり、また世代交代があったり、更には店の主人が代わってはいる。しかしながら、この市場で商売をしている人々が、済州島出身者とその子孫であるという点は変わっていないのは、1つの特徴と言えるであろう。
【図2「朝鮮市場」内の略図】
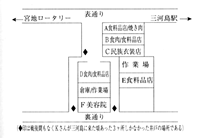
3-2市場の中のヒトとモノ
上で触れたように、昭和24年に1軒の店からスタートしたこの「朝鮮市場」は、戦後50年の中で徐々に形成されたものであった。ここでは、この市場の中で働くヒトと売られるモノについて、A店からD店までの4軒を例にして見て行くことにしよう。
* * * *
大通りに面した所に位置するA商店は、焼き肉屋と食料品店を経営しているが、当初は魚を扱う店であった。A店を初めとしてこの朝鮮市場で扱われる海産物、乾物の一部には、これまで房総半島で活躍する済州島出身のヘニョ(海女)が最近まで店に売りに来ていたらしい(4)。
B商店は、先にも記したように、D店で数年働いた人が後に「乾物屋」として独立し、現在食肉と韓国食品の卸および小売販売を商売の中心としていて、在日二世の夫婦が主となって店を切り盛りしている。食肉の方は、焼き肉の材料を主とし、豚・牛・鳥は勿論のこと、内蔵(肝・舌・ホルモンなど)も扱っている。韓国食品の方では、韓国風の様々な餅やパン、乾物類、そして幾種類ものキムチ、インスタントラーメンなどが売られている。
C店は、チマ、チョゴリ、パヂなどを扱う民族衣装店である(5)。この市場内に店が出来て40年近くになり、経営者も3度変わっているが、すべて済州島出身であり、女性である。店内には、色鮮やかなチマチョゴリが飾られているが、この店で扱っている商品は民族衣装を中心としているもののそれだけではない。枕や布団などの寝具(これも色鮮やか)、座布団などから、アクセサリー、韓国人形、高麗人参や漢方薬、韓国の演歌カセットテープ、そして死者儀礼に使う紙の金まで、扱われる商品は実に様々である(写真1,2)。男性の民族衣装であるッルマギよりは、女性のチマチョゴリの方がよく出るが、勿論晴れ着であるこれらの衣装は結婚式や成人式、または還暦祝いの時などに注文が来ることが殆どである。ここ数年、民族衣装はソウルと東京を行き来する商人(女性)に直接注文して、寸法だけ教えれば、最新式のデザインで仕上げてくれ、日本で作らせるより安く上がると言う。それ以前は、大阪にある問屋から生地を取り寄せ、荒川にいる済州島出身の人に縫製してもらっていたが、縫う人も少なくなり、かつコストも高いため、止めてしまったと言う。また、民族衣装といっても生きている者だけでなく、亡くなった者のための衣装もある。ムーダンが行う儀礼の中で燃やされる衣装(サルオッ)であり、現在の店の主人の話ではその注文が実際かなりあるようであった(6)。高麗人参や漢方薬や、そのような儀礼をする年をとった一世のハルモニらに多くは売られるそうだ。

最後にD商店であるが、先にも記した通り、この朝鮮市場の「最古参」である。現在では、この店を始めたハルモニ(おばあさん)は、今年数えで75才になり、現在三河島でしている商売を始めて46年目である。6人の息子の母親であり、15人の孫のお祖母さんである。1920年に済州島南部のソギポ近くの農村で生まれたが、両親が大阪で商売をするため7才の時に、大阪へ渡った。ll才のときに済州島に戻り、20才までは生まれ故郷で暮らしていたが、25のときに再度大阪へ渡り結婚し、33才までに6人の子供を生んだ。が、6人目の子供を授かって10年後の43才のときに、ご主人が他界され、その後の人生は苦労の連続であったと言う。乾物中心で1人で切り盛りした当初の店も、現在では次男夫婦と末息子が中心になって、食肉と韓国食品(各種キムチ、ヤンニョム、調味料など)を中心とした店になっている。それでも、ハルモニは夕方の忙しいときに接客したり、韓国食品の注文をするなど嫁に負けず活躍していて、まだ「隠居」しようとする気などないらしい。
4.市場の《内》と《外》
以上、市場を構戒する店について、インタビューによる資料からまとめてみた。市場の《内部》は、確かにヒトやモノだけでなく、雰囲気や匂いも、そして飛び交う言葉も、他の商店街とは異なり、《外部》から来る者にとって一種独特である。市場の周辺に住む「日本人」にしても、「キムチなどの韓国の食べ物を売っている」という程度の知識が通常であり、この市場が済州島からの人々で成り立っていることなど知る者は、少ないであろう。
上で記述したそれぞれの商店は、ある程度それぞれの固定した客(タンゴルソンニム)をもっているようで、D店のハルモニの話では、やはりこの付近の済州島出身の在日の人が半分以上であり、遠くは千葉や埼玉から来る客もいるらしい。これに最近韓国から来ている人々(所謂ニューカマーズ new comers)が加わり、更にはキムチ好きの日本人の客といった具合だ。また、日常の食料品として買いに来る客もいれば、チェサ(祭祀)などのため食べ物として大量に買いに来る客もいるとのことだ。民族衣装店の場合、やはり「日本人」の客はごく稀らしい。30年間この市場で店を開いていたKハルモニによれば、やはりタンゴルソンニムと言えば済州島出身者で、「団体の人」と言うことであった。彼女の言う「団体の人」とは総連(在日本朝鮮人総連合会)の構成員である。彼女の話では、東京の民族衣装関係の同業者は浅草と上野にいるが、やはり総連の人で、民団の人の同業者は東京では非常に少ないとのことである。
この本のテーマである「市場」という言葉から連想されるのは、匿名でかつ様々なヒトがモノを介して交差する場所であり、一見この朝鮮市場もそのような場所であるように見えるのだが、店の中で数時間過ごしたり、ハルモニの話を聞いていると、タンゴルソンニムも多く、そうとも言えない気がしてくる。単に“エスニックフード”とか、“日本の中の異文化”という言葉、もしくは視点により、自分とはかけ離れ異化した存在として認識するのではなく、この市場を取り巻く外部(日本社会や朝鮮半島)との諸関係の束に自分との連続性を意識しながら、市場の内外部を丁寧に描く必要があると感じているのだが、それは今後の課題として、今回はこの辺で筆を置くことにする。
【参考文献、資料】
原尻英樹1995「つくりかえられ生産されるドラマー生野に住む「日本入」と「朝鮮人」一」『ホルモン文化』5号新幹社
原尻 他4名1996「コリアンニューカマーズの日本社会への参加」『青丘学術論集』第8号韓国文化研究振興財団
泉 靖一1966「東京における済州島人」『済州島』東京大学出版会
金奉玉1980『高内里誌』在日本高内里親睦会
金栄・梁澄子1988『海を渡った朝鮮人海女』新宿書房
李文雄1990「在日済州人の儀礼生活と社会組織」『民博通信』NO.44(朝倉敏夫訳)
佐藤 健1996「味な放浪記東京・韓国料理編」(毎日新聞2月2日夕刊)
VISUALFOLKLORE1996「東京の中のアジア三河島物語」(MXテレビにて2月29日に放送)
山口昌男1984『祝祭都市 象徴人類学的アプローチ』1984岩波書店
【注】
- 在日韓国人による雑誌(『三千里』など)では紹介されていたが、参考資料で示したように、今年になって新聞やテレビでも取り上げられている。
- 勿論、在日韓国・朝鮮人の定義によってこの数は異なる。単に国籍や言語、文化などの指標から定義を試みたり、主観的な認識を組み入れ定義をすることも可能かもしれないが、済州島と荒川を頻繁に行き来する人々に対して、◎◎入とか◎◎文化と定義するのは非常に難しい。また、一世、二世、三世という概念にしても同様である。
- 現在、母村である済州島の高内里よりも、荒川を中心にして東京に住む高内里出身者の方が、世帯数・人口の上で上回っている。
- 房総半島で活躍する/した海女については『海を渡った朝鮮人海女』に詳しい。
- ここでの記述は主として、昨年まで店の主人であったTハルモニへのインタビューに基づいている。
- 関東地方では、この種の儀礼は荒川の河川敷や埼玉の朝鮮寺、山では高尾山で行われることが多い。